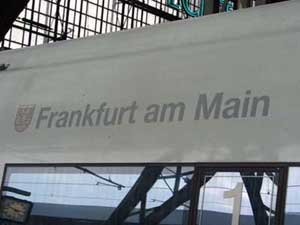| DB BR 403 (50編成) / BR 406 (13編成) NS BR 406 (4編成) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツの車輌 ICE
電気機関車 ディーゼル機関車 蒸気機関車 電車 気動車/蓄電池車 客車 貨車 事業用車 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめに |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3は最高330km/hの高性能と品質の高い車内設備を兼ね備えたドイツ鉄道のフラッグシップである。単電源式の403形と4電源式の406形が開発され、2000年6月より営業運転を開始した。現在はドイツ西部から南部にかけての広い範囲で運用され、406形はオランダ・ベルギー・フランスへの直通運転も行っている。勾配の続く高速新線SFS
Köln - Rhein/Mainに投入するため、ICEシリーズでは初めて動力分散式を採用され、ドイツ国内ではSFS Köln
- Rhein/MainとSFS Nürnberg - Ingolstadtで最高300km/h、フランスLGV 東ヨーロッパ線では最高320km/hを誇る。 ICE 3はその優れた性能・流麗で美しいデザイン・機能的で充実した車内設備により、ICEブランドのスタンダードを確立し、世界を代表する高速列車の一つに数えられる。また、ICE 3をベースとするSiemensの高速列車“Velaro”はドイツの高速列車として初めて海外への輸出にも成功し、スペイン・中国・ロシアにも導入されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登場の背景 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ西部のルール地方はEssen、Düsseldorf、Dortmund、Köln等の大都市が散在する人口密集地帯で、古くから鉱工業が発達している。この地方と、金融の中心Frankfurt
am Mainを結ぶ路線(ライン川左岸線)は旅客が多く、InterCityが1時間に3-4本も運転されるなど、ドイツでも列車密度が最も高い路線の一つであった。しかし、在来線はKöln
- Bonn - Koblenz - Mainz - Frankfurt (M)をライン川沿いに走るため、曲線が多く、南に大きく迂回しており、Köln
- Frankfurt (M)では約2時間15分を要していた。Köln-Frankfurt/Mを結ぶ高速新線は1960年代後半には既に計画されていたが、1995年になってようやく着工され、2002年に開業を迎えた。この高速新線SFS
Köln-Rhain/Mainはライン川の山側、ライン渓谷の地形の険しい地帯を貫く形で建設され、両都市間の距離は214kmから177kmに大幅に短縮された。しかし、コスト削減のためトンネル建設が極力回避されたことから勾配区間が多く、一部には40パーミルの急勾配も介在している。線形の厳しい新線で最高300km/hを実現するには、従来のICE車両以上の性能が持つ専用車が必要であり、全くの新設計で開発されたのが、ICE
3である。 ICE 3開発の目的としては、国際運用の拡大も挙げられる。従来のICE 1もスイスやオーストリアへ直通していたが、フランスやオランダ、ベルギーなどは電源方式が異なるため、直通列車は客車列車に頼っていた。これらをICEに置き換えるためには、多電源式の車両が必要であった。すでにICE 1の登場時から、ICE Mと呼ばれる複電源式車両の計画も存在していたが、結局は実現せず、多電源式の車両の登場が待ち望まれていた。 これらの要求を満たす車両として開発されたのが、ICE 3である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3は当初はICE 2の開発から派生したという意味から、ICE 2.2と呼ばれ、また4電源の国際仕様についてはICE
2.2Mと呼ばれたが、完成が近づいた頃からICE 3 (4電源式はICE 3M)と呼ばれるようになった。形式は単電源仕様車が403形、4電源仕様車が406形である。計画では3電源仕様の405形も存在したが、実際には登場していない。ICE
3の特徴は以下の通りである。 (1) 電車方式 ICE 1やICE 2で採用された動力集中式の車両は、SFS Köln - Rhein/Mainに存在する急勾配を走行するには不向きであり、交流モーターの開発によりモーターの保守の手間が飛躍的に軽減されたこともあって、ICE 3では電車方式が採用された。これにより、軸重が17 t以下に軽減され国際運用に有利となると共に、列車内の空間をより有効に利用できることとなった。 (2) 最高速度の向上 さらなる高速化を目指し、最高速度はICE 2を50km/h上回る330km/hとされた。 (3) 分割・併合を可能とする ICE 3は8両編成で編成長は200mであるが、ICE 2と同様に分割・併合を可能とすることで、幹線のみならずローカル線においてもより効率的な列車運転を実現した。併結した場合の一列車の最大長は400mとされ、従来の駅や工場設備でも対応できる。 (4) UIC規格 ICE 3はより広範な国際運用を可能とするため、DBとフランス鉄道SNCFで合意したUIC505規格に合わせ、ICE 2などの従来車に比べ、車体がやや小ぶりになった。特に、車体幅がICE 2の3,020mmから2,950mmに変更された。 (4) 国際運用への対応 ICE 3では運転室が中央に配置され、左側通行・右側通行いずれの場合にも対応している。ICE 3Mは4電源式となり、ヨーロッパの殆どの国への入線が可能となった。保安装置についても各国に対応しており、広範な国際運用が可能である。 (5) 環境への配慮 環境への影響を極力低減する努力が払われ、特に空調装置は航空機で実績のある空気を媒体として利用するものとなり、フロンなど環境に有害な冷媒が不必要となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994年、DBは93編成の電車を発注した。内訳は単電源式のICE 2.2 (403形) 37編成、4電源式のICE 2.2M (406形)
13編成、ICT(現在のICE-T) 43編成である。1995年にはオランダ鉄道NSもドイツ直通用に4本のICE 2.2Mを発注した。受注したのはSiemensとADtranzの2社で、1編成あたりの価格は、403形が約4000万マルク、406形が約4200万マルクで、ICE
2.2 50編成では総額19億マルクの大型発注となった。ICE 2.2は製作過程で、ICE 3と呼ばれるようになった ICE 3の製作は鋭意進められ、1998年秋には10月末にBerlinで開かれた"Eurailspeed 1998"で、406形の第一編成が公開された。1998年末からはSiemens社所有の実験線で試験運転が開始され、2001年6月1日より営業運転が開始された。 2001年にはDBはICE 3を8編成追加発注を行い、2002年にはさらに5編成が追加された。この403形2次車13編成は、DBがメーカー側に信頼性に問題があるとの理由で受領を拒否したものの(一説にはDB側が資金調達の関係で、故意に受領を遅らせたとも言われる)、2005年11月より順次納入され、11月27日より営業運転に就いた。2006年初頭までに2次車の納入は完了した。 国際運用の拡大に備え、DBは2007年10月にはSiemensにICE 3の追加発注の意向を示していたが、2009年12月17日にDBとSiemensの間で正式な契約が結ばれた。追加編成はSiemensのプロダクトネームでは”Velaro D”と呼ばれており、4電源の8両編成で、15編成が発注され、発注価格は4.95億Euroであった。SiemensのKrefeld-Uerdingen工場で製作され、2011年10月から2012年にかけての納入が予定されている。形式は407形となる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザイン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3のデザインは、ICE-VやTransrapid、さらに最近では500系新幹線のエクステリア等の実績があるNeumeister Designを中心に、Siemens Design、Design Worksが共同で行なった。 ICE 3のデザインはICE-Tと同時に進められ、共通点が多い。両者とも、それまでのICEのイメージを踏襲しつつ、より高級感のある全く新しいデザインが特徴である。当初は運転席をやや後部の高い所に設置し、その前部に展望席を設ける案、あるいは運転室後部のラウンジの座席を線路方向に配置する案などもあったようである。 1995年10月にSiemens社の展示会でICE 3とICE-Tの1:1モックアップが公開された。このモックアップは現在の姿にかなり近いものであるが、入口付近や車内の配色等に一部違いが見られえる。このモックアップは現在はNürnbergのDB博物館で展示されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3は4M4Tの8両編成で、軸配置はBo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'である。1編成の全長は200.320mmで、2編成まで併結して運転することが可能である。以下に編成表を示す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
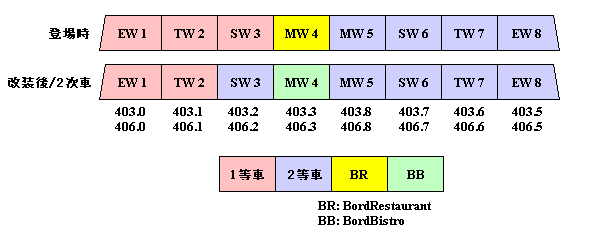 ※ EW: Endwagen (先頭車) / TW: Trafowagen (変圧器搭載車) / SW: Stromrichterwagen (変換器搭載車) / MW: Mittelwagen (中間車) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登場当初は1等車3両・2等車4両・BordRestaurant 1両の構成であったが、2等車の座席不足から慢性的な混雑が問題となり、2002年8月のSFS
Köln-Rhein/Main開業時より1等車2両・2等車5両・BordBistro 1両に変更された。403形2次車は落成時から、この構成に従っている。現在の403形1次車/403形2次車/406形の車両構成を以下に示す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403形 (1次車) 車両構成
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403形 (2次車) 車両構成
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406形車両構成
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403形は"Tz 3xx"(※Tz: Triebfahrzeuge)、406形は"Tz 46xx"と整理されている。Tz 301-337 (403形1次車), Tz 351-363 (403形2次車) / Tz 4601-4613 (406形DB所属), 4651-4654 (406形オランダ鉄道NS所属)が製作された。 以下に編成例を挙げておく。 Tz 337編成: 403 037 + 403 137 + 403 237 + 403 337 + 403 837 + 403 737 + 403 637 + 403 537 Tz 4610編成: 406 010 + 406 110 + 406 210 + 406 310 + 406 810 + 406 710 + 406 610 + 406 510 このように車番の下二桁は通常同じであるが、一部の編成で中間車が組み替えられている例も見られる。 2007年のフランス直通の開始に伴い、406形のうちフランス直通仕様に改造された6編成は以下のように改番された。Tz 4605→Tz 4680 / Tz 4608→Tz 4681 / Tz 4609→Tz 4682 / Tz 4606→Tz 4683 / Tz 4612→Tz 4684 / Tz 4613→Tz 4685。 2010年8月、Tz 4681はNeustadt an der Weinstrase付近で線路上に転落したゴミ運搬車と衝突し、406 081 / 181の2両が深刻な損傷を受け廃車となった。2011年1月にはArnhem - EmmerichでTz 4654が貨物列車と衝突し、406 554 / 654の2両が損傷を受けた。Tz 4681のうち、406 581 / 681の2両は406 554 / 654に代わりTz 4654に連結され、Tz 4653は2012年1月1日付けでNSからDBに移籍した。 現在の使用されている編成は以下の通りである。 403形 (DB): Tz 301-337, Tz 351-363 406形 (DB): Tz 4601-4604, Tz 4607, Tz 4610-4611, Tz 4654, Tz 4680, Tz 4682-4685 406形 (NS): Tz 4651-4653 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3の車体はリブのないアルミ合金製である。サイズは広範な国際運用に備え、DBとSNCFが合意したUIC505規格に合わせて従来のICEに比べ一回り小さくなり、幅2,950mm、長さ先頭車で25,675mm、中間車で24,775mm、1編成辺りの長さは200mとなっている。先頭部は空気抵抗や風・対向列車に対する対応、騒音などが考慮され、流線形がよりシャープで長い、スピード感の強調されたものとなった。出入口は高さ550mmと760mmのプラットホームに対応している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗装 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEシリーズにはライトグレー (RAL 7035)をベースに赤色Verkehrsrot (RAL 3020)、裾部はグレー (RAL 7039)という共通の塗装が施されており、ICE
3もこれを踏襲している。デザイン的にはICE-Tに近いが、ICE 3は赤帯が先頭まで回り込んでいるのが特徴である。先頭車(EW 1/EW 8)と中間車MW
4側面にはグレー (RAL 7038)で"ICE"のロゴが入れられている。MW 4には"BordRestaurant"のロゴも描かれていたが2002年の改装工事に合わせ、"BordRestaurant"の表記は、"BordBistro"に変更された。406形については先頭車側面に編成番号も書き加えられている。またDBはICE編成には都市名を愛称として付けており、その都市の市章が先頭車側扉の横に描かれるようになった。2007年春からは”ICE”ロゴをDB
Typeと呼ばれる新しい字体に変更した車両が試験的に登場し、2007年末以降、全車両を対象に新字体への変更が進められている。 NS所属の編成については、DBマークの代わりに紺色のNSマークが描かれており、"BordRestaurant"表記ではなく単に"Restaunrat"と紺色で描かれていた。Bistroに改装された際には、この表記は"Bistro"となった。2008年からはNSマークの代わりに、赤色の”NS Hispeed”のロゴとなった車両も見られる。 また先頭車側面の車端部には、2000年Hannoverで開催されたExpo 2000、2006年のサッカー・ドイツワールドカップの広告が入れられた。また、2007年には406形の先頭部側窓の上部にドイツ・Heiligendammで開催されたG8-Summit 2007をPRするロゴが入れられた。2005年にはDBとT-MobileによりICE車内での無線LANサービスが開始され、Tz 301とTz 311の2編成に対し"HotSpot"、"www im ICE"などのロゴが入ったPR塗装が施された。現在は無線LANサービス対応編成について、側扉横にPRロゴが入れられている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気・機械関係 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403形はAC 15kV 16.7Hz(ドイツ・スイス)のみに対応しているが、406形は四電源式でAC
25kV 50Hz(フランス・オランダ・ベルギー)、DC 1.5kV(オランダ)、DC 3kV(ベルギー)にも対応している。電源方式の変更は停車時でも走行時でも可能である。 ICE 3には試作車は存在しないが、最高360km/hを誇る410形ICE-Sにより電気・機械関係の試験が行われた。 動力車(EW 1/SW 3/SW 6/EW 8)には、定格出力500kW、最高6,000rpm、ギア比2.78:1の空冷式三相誘導電動機がそれぞれ4基搭載されている。1編成では16基の主電動機により、交流区間での編成出力は8,000kWとなり、重量当りの出力は20kW/tとICE 2の2倍に達する。変換器にはGTO-PWRを使用し、GTOモジュールの冷却は水冷式となっている。制御装置にはSIBAS 32が採用されている。 集電装置は従来のICEで実績のあるシングルアーム式のDSA 350SEKを改良したDSA 380が採用された。403形にはドイツ・オーストリア向けのDSA 380Dのみが搭載されているが、406形には各国の仕様にあわせたDSA 380F、DSA 380Gも搭載されている。 ICE 3には3種のブレーキが装備されている、すなわち電力回生ブレーキ、渦電流ブレーキ、ディスクブレーキである。電力回生ブレーキは、ICE 3のブレーキシステムの中心をなす。すなわち、最大300kNものブレーキ力を発揮し、また停止直前まで作用する。これによりディスクブレーキの使用が抑えられ、ディスクの磨耗を軽減している。 渦電流ブレーキは、ICE 1やICE 2では動力車のみに補助的なブレーキとして装備されているに過ぎなかったが、300km/h以上の高速でも大きなブレーキ力を発生し、しかもディスクブレーキのような磨耗が殆どない利点を持ち、改良が進んだことから、ICE 3では付随車全車(TW 2/MW 4/MW 5/TW 7)に装備され、電力回生ブレーキに次いで重要な役割を果たしている。 台車はICE 2で用いられたSF 400台車をベースに、高速走行に対応するために改良が加えられたSF 500台車が用いられている。この台車は410形中間車に搭載され、ICE 1に連結して長期耐久試験が行われた他、ICE-Sでも各種試験が行われた。なお、動力車の台車には電力回生ブレーキの他に1軸あたり2台のディスクブレーキが、付随車の台車には渦電流ブレーキとディスクブレーキ(403形:1軸当り2台 / 406形:1軸当り3台)が搭載されている。 先頭車にはScharfenberg密着自動連結器が装備され、2編成を併結することも可能である。連解結は全自動で行われる。ICE-TやICE-TDと併結することも可能であるが、実際の運用ではICE 3同士の組み合わせのみが存在する。 保安装置としてはDBが用いているSifa/LZB90/PZB80の他、406形はNS用のATB EG/ATB NG、SNCB用のTBL 1/TBL 2/Memor、SBB用のZUB 121/ZUB 262を搭載している。後述するフランス直通用406形は後にSNCF用のTVM/KVBも搭載されている。また、403形/406形とも当初からETCS(European Train Control System)の搭載準備がなされていたが、2009年6月14日に開業したベルギーの高速新線HSL 3 (Liege - Aachen)で保安装置としてETCS採用されたため、Tz 4601-4604, 4607, 4610-4611, 4651-4653にETCS対応機器が搭載された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車内設備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転席はICE 1やICE 2では右側に設けられていたが、ICE 3では中央に配置されている。これはICE 3の国際運用に際して右側通行・左側通行いずれの場合にも運転士の視界を確保するためである。インストルメントパネルは、乗客が眺めることも考慮され、より美しい造形が施されている。計器パネルは、中央にアナログ式の牽引力・ブレーキ力計(%で表示)と速度計が配され、その左右はタッチパネルで、各種の情報を取り出したり設定を行うことができる。操作パネルには、左側に速度設定レバーとマスコンが、右側にブレーキが配されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調装置は航空機で実績のある、圧縮空気を媒体として利用したエアサイクル式となり、フロンなど環境に有害な冷媒が不必要となった。 ICE 3の客室は、当初は1等3両・2等4両・BordRestaurant 1両という構成であった。 客室設備の最大の特徴は、運転室後部に設けられたコックピット・ラウンジである。コックピット・ラウンジは1等・2等双方に存在する。運転室とは透明なガラスで仕切られているのみであり、乗客はここから運転室とその先の前面窓に広がる眺望を楽しむことが可能である。仕切りとなるガラスは特殊で、カーテンや視界を遮るものは何もない代わりに、電気的にスイッチ1つでガラスそのものが透明から半透明になるという仕組みを持っている。なお、この仕切りの中央部はドアとなっており、運転士はここから出入りする。 1等車は4人用ないし5人用コンパートメントとオープン区画からなる。オープン区画は座席が1+2列で配されており、シートは本革張りとなっている。大半の座席については、シート背面にテレビが設置されており、映画チャンネルとマガジンチャンネル(各種情報を放映)を楽しむことができる。テレビのついていない席は、大きな固定式テーブルを挟んで向い合わせに座席が設置されている。 なお、かつては1等・2等も喫煙可能な車両が存在したが、2007年9月からは全面禁煙となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2等車はオープン区画のみで、座席が2+2列で配置とされた。シートはダークブルーのモケット張りで、軽快感を出しながらも高い品質感の仕上がりとなっている。大きな固定式テーブルを挟んで、向い合わせの座席も設置されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デッキ部分は木目調を活かした高級感のあるデザインとなっている。電光式の広告が掲示されているが、トイレの出入口とともに、デッキのデザインと上手く調和した美しいものとなっている。また、車内情報システムFISの端末も設置されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1等・2等の全座席にはオーディオプログラム用のイヤホンジャックが、また座席上部にはLED予約表示機がそれぞれ設けられている。オーディオプログラムはクラシック音楽・ポップ/ジャズ音楽・子供向けチャンネルの3チャンネルと、ラジオ3チャンネルが用意されている。この他、クローゼットや荷物棚も設置されている。 その他、BordRestaurant、家族用コンパートメント、Service-Point、身障者用の設備、カード式公衆電話等の設備もあるが、詳しくは車輌別の項で取り上げたい。 定員は登場時は403形では1等141人、2等250人、BordRestaurant 24人、車椅子席1人の計416人、406形では機器配置の関係でやや少なく1等車136人、2等車244人、BordRestaurant 24人、車椅子席1人の計405人であった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改装 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登場当初は1等車3両・2等車4両・BordRestaurant 1両の構成であったが、2等車の座席不足から慢性的な混雑が問題となり、2002年8月のNBS
Köln-Rhein/Main開業を契機に改装工事が行われた。 改装工事は2002年よりHagenとDelitzschの工場で順次行われ、12月にはほぼ完了した。 1等車1両が2等車に変更され、またBordRestaurantもBordBistroに改装されて一部が2等席となり、1等車2両・2等車5両・BordBistro 1両の編成となった。また2等車のシートピッチが970mmから920mmに縮小され、座席数が増加している。なお、改装の結果、2等車にもコンパートメントが登場した。 定員は403形では1等98人、2等343人に、406形では1等93人、2等338人となり、大幅な定員増が実現された。 改装工事により、供食サービスに変更が加えられた。Restaurantを廃止した代わりとして、1等車ではシートサービスを、2等車では"am Platz-Service"と呼ばれる車内販売の充実が図られた。ただし食堂車の廃止は不評であったため、BordBistro車の座席部分のテーブルにテーブルクロスが掛けられ、メニューも置かれてRestaurantとして利用できる。 なお、2016年からはリニューアル工事が開始され、座席の交換や各種情報を提供するLCDが設置される予定である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改良工事 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3は登場以来様々な問題が生じ、特に2002年12月に本格的に運用されてからはトラブルが目立つようになったため、DBやメーカーはその対策に追われることとなった。 2002年10月24日、ICE 882として走行中の2編成併結列車がGoettingen駅近くを約50km/hで走行中に連結がはずれる事故が発生した。前後の編成とも非常ブレーキが作動したため、幸いにも怪我人も発生せずに済んだ。原因はメーカーの製造不良とされ、対策も成された。その後はこの種のトラブルは起きていないが、他にも連結の際に、自動連結装置がフリーズしてしまうトラブルが頻発した。これは、ソフトに問題があると考えられ、改良が施された。 主電動機に不具合があるとされ、約半数については製造を担当したBombardierにより交換された。 2003年夏、ヨーロッパを猛暑が襲った。この夏、ICE 3の空調装置に故障が頻発し、社会問題化となった。ICE 3の空調はエアフィルターが汚れると装置の吸気力が強まり、過熱を防ぐため自動停止した。空調は車両ごとに制御する方式が取られているため、空調装置が故障した車両の乗客を他の車両に移したり、あるいは無料で飲物を配ったり、あるいは割引券を配布する等の対策が取られた。抜本的な対策として、2003年秋から空調装置が改造された。これに伴い、車端部にやや不格好なクーラーキセが設置された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3の最大の問題は渦電流ブレーキであった。渦電流ブレーキのコイルに水が入り込んでショートし故障が頻発した上、ブレーキの磁力が軌道上の金属物を破壊したり、保安装置に影響を与えるトラブルがみられた。渦電流ブレーキが故障すると、自動的に最高270
km/hに抑えられこのため、安全上の問題はないものの、列車遅延の原因となった。また、渦電流ブレーキへの対策の取られていない路線では渦電流ブレーキが使用できず、そのためNBS
Köln-Rhein/Main以外では最高220km/h、改良新線では最高160km/hに制限された。 ベルギー直通が開始する際には、この渦電流ブレーキと、高速走行時にバラストが巻き上げられ機器を破壊することが問題となり、当初はベルギー国内の高速新線HSL 2への乗り入れを拒否された。このため、床下にスポイラーが設置された。2004年12月には高速新線への乗り入れが許可されたが、路線の規格は最高300km/hであるものの、ICE 3は250km/hに制限されている。 DBとT-Mobileが提携し、2005年12月20日からDortmund-Essen-Kölnで試験的に"HotSpot"と呼ばれる無線LANサービスを開始した。対象になった区間はDortmund-Essen-Kölnで、Tz 304/305/325/334/335に対し、無線LAN関係の設備が搭載された。このサービスは拡大され、他の編成に対しても順次対応工事が行われている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前述の通り、DBは403形13本の追加発注を行った。この2次車は、初めから1等車2両・2等車5両・BordBistro
1両の編成で登場した。車内は1次車を改装したものとほぼ同じであるが、1次車のSW
3 (403.2形)でみられた2等コンパートメントがないため、座席数が増加した。また、1等車のオーディオ設備が廃止された。BordBistroのRestraunt部にも違いが見られるが、詳しくは車両別の項で述べる。外観ではでの差異は小さいが、前照灯がLEDとなり、車端部の空調装置が1次車よりも流麗で空気力学に叶った形状となった。定員は1等車98人、2等車360人、その他16人である。2次車は2005年11月より営業運転に就き、現在も1次車と共通に運用されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE 3MF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEのフランス直通運転はDBの悲願であり、その研究は1990年台前半から行われていた。2001年にはフランスでICE
3Mの走行試験が開始されたが、様々な相違点を解決し、ようやく直通運転が実現したのは2007年6月のことであった。DB所有の406形13編成のうち6編成にフランス直通に対応するための改造工事がBombardierのHennigsdorf工場で行われ、2006年7月から2007年4月にかけて順次落成した。フランス直通用の編成は”ICE
3MF”と呼ばれ、80番台に改番された。改番された編成は、Tz 4605→Tz 4680 /
Tz 4608→Tz 4681 / Tz 4609→Tz 4682 / Tz 4606→Tz 4683 / Tz 4612→Tz 4684
/ Tz 4613→Tz 4685 である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的な改造内容を以下に占めす。 - フランスの信号システムに対応するため、TVM430、KVBが搭載された。Mata, - 運転台上部に車内信号表示が追設された。 - 運転記録システムATESSが搭載された。(TW2/TW7の台車からの測定情報がATESSに送られる。) - MW4/MW5に屋根上の降圧引き通し線の異常感知器が設けられた。(異常電流が感知されると、自動的に引き通し線の電流が遮断される。) このシステムのための変圧器も追設された。 - 高速走行時に、空気の乱流に伴うバラスト飛散による機器の破壊を防ぐため、車両妻面や台車にディフレクターが設けられた。 - 渦電流ブレーキが地上設備に影響を与える可能性が指摘されたため、渦電流ブレーキは高速新線LGV東ヨーロッパ線のみでの使用に限定された。通常、渦電流ブレーキは150km/hで失効するが、フランスでは220km/hで失効するよう変更された。 - 緊急時や警察用の設備が追加された。 この他にも、フランスの規定に合わせ、客室設備にも細かい変更が加えられ、改造工事は非常に多岐に及んでいる。機器の搭載に伴い、座席数は6席減少した。1編成あたりの改造費用は800万Euroである。 2007年6月10日からFrankfurt/M - Paris間での営業運転が開始され、フランス国内の高速新線LGV東ヨーロッパ線では最高320km/h運転を行っている。ただし、車軸トラブルなどもあり、ICE 3MFの編成数は慢性的に不足しており、TGV-POSによる代走などでしのいでいる状況である。 2010年末にはLGV東ヨーロッパ線にETCSが導入される予定で、ICE 3MFにもETCSの搭載工事が行われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両各論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●EW 1 (403.0/406.0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力付制御車。28/38号車で、車内は1等車。 運転室後部が2人掛け3列・1人掛け2列の8席が設けられたコックピットラウンジであり、デッキを挟んで、その後部がオープン区画で1等席が42席設けられている(406形では機器の関係で1列少ないため、38席)。 なお、コックピットラウンジが喫煙席、オープン区画が禁煙席でされていたが、現在は全車禁煙となった。また"Ruhezonen (Quiet zone)"が設けられており、携帯電話の使用が禁止されている。 2次車もほぼ同じ仕様である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●TW 2 (403.1/406.1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付随車。27/37号車。DSA 380D形パンタグラフ(DB 15kV AC, NS 25kV AC用)が搭載されている。 車内は4人用コンパートメント1室、5人用コンパートメント2室とオープン区画からなる。オープン区画は403形では2人掛け11列、1人掛け10列の座席が設置されているが、406形では2人掛けが1列少ない。この他にトイレが2室ある。 改装工事でも、特に変更は加えられていないが、5人用コンパートメントが6人用に改装されるようである。 この車両は禁煙車で、携帯電話の通話が行いやすくなっている。 2次車は、コンパートメントが4人用コンパートメント1室、6人用コンパートメント2室となる以外は大きな変更はない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●SW 3 (403.2/406.2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力車。26/36号車。406.2形にはDSA 380G形パンタグラフ(NS 1.5kV DC, SNCB 3kV DC用)が搭載されている。 車内は当初は1等車で、座席配置はTW 2と同様であった。406.2形についても座席数は403.2形と同じで、2人掛け席が11列あった。 改装工事では、この車両は2等車に改装された。座席は全て交換され、4人用個室は5人用に、5人用個室は6人用になり、オープン区画は座席が2+2配列で44席となった。結果として、この車両の定員は61人に増えた。 この車両は禁煙車で、携帯電話の通話が行いやすくなっている。 2次車ではコンパートメントは設置されずオープン区画のみとなり、2+2配列で74席が設置されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●MW 4 (403.3/406.3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付随車。25/35号車。406.3形にはDSA 380F形パンタグラフ(SNCF 25kV AC, SBB
15kV AC, SNCB 25kV AC用)が搭載されている。車体の両側面には、赤字で大きく"BordRestaurant"のロゴが書き込まれていた。 登場時の車内はBordRestaurantとなっており、車両中央部が厨房と売店で、両端が24席のレストラン(4人席x4 / 2人席x4)と、小さなテーブルが2脚設置されたビストロから構成されていた。内装は木目調の開放的な雰囲気で、レストランの赤色のベンチやテーブルライトとあいまって、TEE時代の伝統的な食堂車を彷彿とさせた。ビストロの横には"Service-Point"と呼ばれる区画があり、FAXやAudio関係のサービス機器が集められた。また、"Service-Point"にはカウンターが設けられており、車掌が乗客に各種の案内を行うことが可能な構造となっている。さらにテレホンカード専用公衆電話も設置されている。 2002年の改装工事で、最も大きな変更が加えられたのが、この車両である。具体的にはBordRestaurantをBordBistroに変更されることになり、レストラン部分のテーブル2列分(4人席x2 / 2人席x2)がテーブル・腰掛とも撤去され、代わりにビストロ用の小型テーブルが4脚設置された。残るテーブル2列分については、腰掛が通常の2等車用のシートに交換された。結果として、この区画は1+2列の12席分の2等車となった。ただしテーブルには特に変更が加えられず、テーブルライトも健在である。ビストロとはガラス板で仕切られた。この改装に伴い、車体側面のロゴも"BordBistro"変更された。なお、BordRestaurantの食堂部分で用いられていた赤色の椅子の市販された。一部はKölnにあるOdeon-Kinoという映画館のカフェで再利用されている。 ただし、食堂車の廃止は不評であったためか、2等席区画のテーブルにはテーブルクロスが掛けられ、メニューも置かれて食堂として利用されている。この車両も禁煙車である。 2次車では2等席の区画が2+2列となり、座席数が16席となった。テーブルランプは設置されていない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●MW 5 (403.8/406.8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付随車。24/34号車。406.8形にはDSA 380F形パンタグラフ(SNCF 25kV AC, SBB
15 kV AC, SNCB 25kV AC用)が搭載されている。 車内は2等車で、2+2配列のオープン座席44席の他、6席の家族用コンパートメント1室、トイレ2室(1室は身障者対応)という構成であった。またオープン区画の端(家族用コンパートメントの隣)には車椅子を固定できる区画があり、ジャンプシートも2席設置された。 家族用コンパートメントは2種のコンセプトでデザインされており、それぞれのテーマは"Tempo, klein Schnecke"、"Kind Memory"となっている。403 801-403 819 / 406 801-406 806 / 406 851-406 852は前者のデザイン、403 820-403 837 / 406 807-406 813 / 406 853-406 854は後者のデザインを採用している。 身障者用トイレは車椅子でも利用可能な大きさになっており、またオムツ交換台も用意されている。 改装工事により、座席が1列分増やされ、オープン区画は48席となった。 この車両は禁煙車である。 2次車は座席配置がわずかに異なり、2席多い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●SW 6 (403.7/406.7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
動力車。23/33号車。406.7形にはDSA 380G形パンタグラフ(NS 1.5kV DC, SNCB 3kV DC用)が搭載されている。 車内はオープン区画の2等車で、車内には基本的に2+2配列で68席設置された。デッキとの間にはトイレが2室設置された。 改装工事によりシートピッチが縮められ、座席配置の変更により74席に増えた。この車両は禁煙車で、携帯電話の通話が行いやすくなっている。 2次車もほぼ同じ仕様である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●TW 7 (403.6/405.6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付随車。22/32号車。DSA 380D形パンタグラフ(DB 15kV AC, NS 25kV AC用)が搭載されている。 車内はSW 6と基本的に同じである(406.6形は機器の関係で2席少ない)。改装工事によりSW 6と同様に変更された。この車両は喫煙車に指定されていたが、現在は全車禁煙となった。 2次車もほぼ同じ仕様である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●EW 8 (403.5/406.5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力付制御車。21/31号車で、車内は2等車。 運転室後部が10席のコックピットラウンジであり、デッキを挟んで、その後部がオープン区画で2等席が54席設けられている(406形では機器の関係で1列少ないため、50席)。 改装工事で、シートピッチが縮められたのに伴い、オープン区画は58席に増えた。 なお、この車両は禁煙車であり、また"Ruhezonen (Quiet zone)"が設けられており、携帯電話の使用が禁止されている。 2次車もほぼ同じ仕様である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験・デモンストレーション走行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3は1998年秋に第一編成が完成し、Siemens社のWegberg-Wildenrath実験線を皮切りに、Hannover
- Wuerzburg・Hannover-Berlin高速新線にて試験が行われた。 2001年9月3日にはHannover-Berlin高速新線のうちWolfsburg-Rathenow間110kmで、試験列車が369,44km/hを達成した。この試験列車には、ドイツ鉄道社長Hartmut Mehdorn氏も乗車していた。規定では営業列車で330km/h運転を認可されるためには、試験で363km/h走行を行う必要があり、これを満たしたこととなった。 ICE 3を用いたNBS Köln-Rhein/Mainにおける試運転は、2001年10月22日より開始された。当初は走行可能が区間が限定されていたため最高200km/hに抑えられたが、12月には最初の300km/h運転が行われた。救援用に配置された216形との連結試験なども行われ、2002年夏には乗務員の習熟訓練も開始されて、開業に備えた。 7月25日にはNBS Köln-Rhein/Main開業の記念式典がFrankfurt Hbfで行われた。これに合わせて、招待客やプレス向けに2本の特別列車が運転された。これらの列車は高速新線上で300km/hにて並走運転を行い、開業を盛り上げた。さらに7月30日にはPorz-Wahn駅付近で5本のICE 3を60km/hで並走させるデモンストレーションが行われた。 2006年5月13日にはNBS Nuernberg - Ingolstadt開業を記念して、2本の特別列車が運行された。"Bahn frei!"という赤いロゴが入れられた編成が使用され、ここでも300km/hでの並走運転が行われた。 国際運用に備えて、近隣諸国でもICE 3の試運転が行われた。2001年5月1日から15日にかけ、403形1本がスイス各地で試運転を行った。試運転はGuemlingen-Thun間を皮切りに、Bern近郊のGrauholzトンネルでの200km/h走行試験を経て、Bellinzona-Airolo間のGotthardトンネル、さらにローザンヌ地方でも試験が行われた。スイス国内での運転については既に認可されているが、現在のところICE 3はBasel SBBまでしか乗り入れていない。 ベルギーでの試運転も、406形を用いて何度か行われており、2001年12月にはTz 608編成がWelkenraebt-Aachen等を走行した。 フランスでは2001年6月から、406形1本(Tz 4608)が試運転を行った。試運転はBlainville-Reding間で開始され、その後StrasbourgをベースにStrasbourg-Mulhouse間で8月まで続けられた。2002年9月にはTz 4603編成がStrasbourgをベースに試運転を行った。続いて、Tz 4608編成が2002年11月8日に今度はLilleに送られ、12月3日よりLille - Calais高速新線にて試運転が行われ、320km/h走行試験も行われた。その後もLGV東ヨーロッパ線を中心に試運転が継続され、2007年3月8日までの6年間でフランスでの走行距離は12,0000kmに達し、2800万Euroを要した。2008年5月31日にフランス鉄道局よりICE 3MFの運行認可が下りた。 2007年6月10日のFrankfurt - Paris直通運転開始を前に、5月26日に記念列車ICE 13032がTz 4680編成により運転され、8時29分にFrankfurt/M Hbfを出発し、35分の13時32分にParis Gare de l'Estに到着した。DBのMehdorn社長も添乗し、Paris東駅入線の際にはStuttgart発の特別列車TGV 13036 (TGV-POS 4407編成)と同時に進入する演出がなされた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年4月1日にICE 600 (403形Tz 321編成)はIstein付近を80km/hで走行中に、軌道上に止まっていたトラクターと衝突、脱線した。この事故でトラクターの運転手が重傷を負ったほか、乗客二人も軽傷を負った。 2008年5月16日にはICE 9554 (406形Tz 4682編成)がLGV 東ヨーロッパ線のParis近郊を走行中に主電動機のベアリングの異常からから火災が発生した。負傷者はなく、乗客はTGVに乗り換え、Parisへ向かった。Tz 4682編成はこれにより年末まで運用から外れた。 2008年6月にはTz 4684編成がICE 9555として運行中にKaiserslautern近郊で工事用車両と接触してダメージを負い、一時的に運用を外れたこともあり、ICE 3MFの編成数が不足し、TGV-POSが代走したり、ICE 3MFによる運行区間を短縮し機関車牽引列車を接続させるなどの措置がとられた。 2008年7月9日にはICE 518 (Tz 310編成)がKöln Hbfを発車した直後に脱線した。まだホームを離れていない状態で低速であったことから、負傷者はなかった。原因は動力車403 710の車軸の破断であった。ICE 3の車軸の超音波検査は300,000走行キロごとに行われていたが、7月11日からは120,000走行キロ毎の音波検査が義務付けられ、さらに同じ材質の車軸を用いている車両については60,000走行キロ毎の検査が義務付けられた。ICE 3全67編成のうち、61編成はこの規定変更により運用から外れ、ICE 3使用列車の運行区間の短縮や運休、ICE 3以外の車両による代走が行われたが、ダイヤは大幅に乱れた。特に7月11日はICE 3の残った6編成がKöln - Frankfurt(M)を往復するのみであったが、検査終了とともに順次運用に復帰し、7月15日には一部列車の編成短縮、運行区間短縮を残すのみとなった。7月20日には緊急検査は終了し、異常は発見されなかった。車軸への負担を減らすため、TW7 (22/32号車)の渦電流ブレキーをカットする措置も一時的に取られたが、後に戻されている。 2008年10月初旬にはICE-Tの定期検査で車軸に2mmの亀裂が発見された。これを受けて、連邦鉄道局EBAはDBに超音波検査の間隔を半減するよう求めた。しかし、30,000走行キロ毎の超音波検査に対応する体制がなく、結果的にICE 3の編成数が再び不足することとなった。DBは編成短縮や、一部区間の代替列車の運転を行い、11月中旬からは2009年6月のダイヤ改正までは暫定ダイヤで運行された。2012年2月から新たに設計された車軸の試験が開始され、2013年末にEBAより認可が下りた。2014年初頭から2年間で車軸の交換が行われる予定である。 2010年4月17日SFS Köln-Rhein/MainでICE 505として運行されていたTz 325の27号車の側扉が外れ、離合したICE 612のBordBistroに衝突する事故が発生した。側扉の留め方が不適切であったことが原因と判明し、2週間かけて全編成の側扉が検査された。また定期検査の項目にも加えられあ。 2010年8月、Tz 4681はICE 9566として運行中に、Neustadt an der Weinstrase付近で線路上に転落したゴミ運搬車と衝突し、406 081 / 181の2両が深刻な損傷を受け廃車となった。 2011年1月にはArnhem - EmmerichでICE 123として運行されていたTz 4654が貨物列車と衝突し、406 554 / 654の2両が損傷を受けた。Tz 4681のうち、406 581 / 681の2両は406 554 / 654に代わりTz 4654に連結され、Tz 4653は2012年1月1日付けでNSからDBに移籍した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velaro D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemensはスペイン・ロシア・中国に対し、ICE 3をベースとした高速列車”Velaro”をのセールスを成功させた。DBはICE 3の編成数不足と国際運用の拡充に備え、2008年にSiemensに対してVelaroを発注した。この新車両は”Velaro D”と呼ばれ、形式は407形となったが、ICE 3の改良型に位置づけられた。 407形は4電源式の8両編成(全長200m)で、出力は交流区間で8,000kW、直流区間で4,200kW、最高320km/hとなる。2編成併結での運行や、ICE 3との併結も可能になる。車体は高速列車に求められるTSIスタンダートを満たす。空気力学的な面から先頭デザインは変更され、特に前照灯周囲は406形とはかなり異なる。機器配置や座席配置も見直され、ラウンジが廃止された一方で、BordRestaurantが設けられた。406形より定員が増え、460名となった。 Velaro Dは15編成が発注され、後にTz 4681の代わりとしてさらに1編成追加発注された。当初の予定では2011年12月に就役し、LGV Rhein-Rhoneが開業するフランスへの直通運用などに用いられる予定であったが、トラブルが頻発したためEBAからの認可が得られず、納入が大幅に遅れた。この納入遅延の補償として、さらの1編成がSiemensからDBに納入されることになり、最終的には17編成が製作される予定である。407形は2013年12月に4編成体制で営業運転を開始した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3は全車両がBW München-Suedに配置され、2000年6月1日より営業運転に就いた。当初は403形17本、406形3本という体制で、Hannoverで開催されたExpo2000の会場に近いHannover
Messe/Laatzen駅と、Amsterdam・Basel・Köln・München・Frankfurt/M Flughafen等を結ぶ万博輸送列車"EXE"や"ICE"に投入された。この万博運用は10月末まで続いた。 2001年ダイヤ (2000年11月5日改正)で、それまでのECに代わり、ICE Linie 5A Köln Hbf-Amsterdam CSが新たに設定され、7往復(1往復はFrankfurt Hbf - Amsterdam CS)のICE("ICE International"と呼ばれた)の運転が406形により開始された。この路線は路線改良が及んでいないため、わずかな区間で200km/hに達するのみであったが、Emmerichでの機関車交換が省略され、ECに比べても分程度所要時間が短縮された。なお、ICE Line 5Aの運転開始に先立って9月末から、ECは406形による運転に順次置き換えられた。この新ダイヤに合わせる形で、11月に406形は全車BW Frankfurt/M Griesheimに転属した。なお、NS所属の406形4編成もDB車と共通運用が組まれた。 また、403形はICE 2に代わり、ICE Line 4 Hamburg-/Bremen-Hannover-Wuerzburg-Münchenに順次投入された。この路線では、HamburgとBremen発着の列車がHannoverにて連結・解結を行った。Hannover-Würzburg間の高速新線では渦電流ブレーキが信号機器に影響を与えるとされ、最高速度が230km/hに制限されたが、ダイヤ上は問題にならなかったようである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3は登場後しばらくは、その性能を持て余していたが、2002年8月1日にSFS Köln-Rhein/Mainが開業し、ICE
3による最高300km/hの運転が開始された。まずはFrankfurt Hbf-Köln Hbf間を結ぶ1日7往復のシャトル列車が設定され、両駅間を76分程度で結んだ。9月15日に15往復へ増便され、概ね1時間間隔の運転となった。シャトル列車ではBordRestaurantが廃止され、供食サービスはBistroと車内販売となった。この区間には特別運賃が課されたが、ライン川左岸線に比べ所要時間が半分程度となったこともあり、高い乗車率を維持した。 2003年ダイヤ (2002年12月15日改正)で、いよいよSFS Köln-Rhein/Mainの本格運用が開始され、ICEネットワークは刷新された。NBS Köln-Rhein/Mainを経由して各都市を結ぶ路線が多数設定され、全てICE 3による運転となった。 -ICE Linie 40 Münster Hbf - Essen Hbf - Köln-Deutz - Limburg Süd - Frankfurt Flughafen - Frankfurt/M Hbf -ICE Linie 41 Dortmund Hbf - Essen Hbf - Köln-Deutz - Montabaur - Frankfurt Flughafen - Frankfurt/M Hbf -ICE Linie 42 Dortmund Hbf - Essen Hbf - Köln Hbf - Siegburg - Frankfurt Flughafen - Mannheim Hbf - Stuttgart Hbf - München Hbf -ICE Linie 43 Dortmund Hbf - Wuppertal Hbf - Köln Hbf - Siegburg - Frankfurt Flughafen - Mannheim Hbf - Karlsruhe Hbf - Basel SBB -ICE Linie 45 Köln Hbf - Montabaur - Limburg Süd - Wiesbaden Hbf - Mainz Hbf - Mannheim Hbf - Stuttgart Hbf -ICE Linie 78 Amsterdam CS-Duisburg Hbf-Köln Hbf-Frankfurt Flughafen-Frankfurt/M Hbf -ICE Linie 79 (Bruessel Midi-Aachen Hbf-)Köln Hbf-Frankfurt Flughafen-Frankfurt/M Hbf 以上の7路線は2時間間隔で運転された。Linie 40とLinie 41、Linie 42とLinie 43、Linie 78とLinie 79はそれぞれ1時間ごとに交互に運転されるため、Essen Hbf-Frankfurt Hbf・Köln Hbf-Mannheim Hbfは1時間毎の運転となり、これに後述するLinie 78とLinie 79が加わり、Köln - Frankfurt/M間はほぼ20分間隔の運転となった。 Linie 42と43はKölnで併解結を行い、Köln以北は1編成単独、Köln以南は2編成併結で運転された。運用上はLinie 42とLinie 45に密接な関係があった。すなわち、Linie 42のMuenchen発の列車はKöln Hbfに到着すると切り離されて、1本はDortmundへ直通し、1本は約20分の停車の後、Line 45としてStuttgartへ向かうのである。逆方向についても同様である。この柔軟な車両運用は、皮肉にも列車遅延の際に、影響を大きくする原因になった。 Amsterdam発着は1日5往復、Bruesse発着は1日3往復設定され、Köln Hbf-Frankfurt Hbf間では1時間間隔の運転であった。高速新線区間はノンストップであり、Köln Hbf-Frankfurt Hbf間を所要約70分で結ぶこととなった。 Bruessel直通は、DBとSNCBの交渉が難航し実現が危ぶまれた。これは406形の渦電流ブレーキが発生する磁力により軌道上の機器に障害が生じる可能性が指摘されたためであり、結局Bruesel直通開始当初はLeuven-Liegeを在来線経由とすることとなった。このため、高速新線を経由するThalysに比べると、Bruwssel Midi-Köln Hbfでは所要時間は約15分長く、Frakfurt/M-Bruesselでは3時間46分を要した。 12月15日以降、ICE 3には数多くのトラブルが報告された。運行上特に問題となったのは渦電流ブレーキと連結器のトラブルの頻発であった。渦電流ブレーキにトラブルが生じると最高速度は自動的に270km/hに制限され、列車遅延の大きな原因になった。また連結器のトラブルで、本来併結するはずの列車が続行して運転されることが頻発している。さらにBrüssel行のICEでは、国境のAachenで信号の切り替えがうまくいかず、遅れが発生したり、Aachenで列車の運転が打ち切られた例もあった。 トラブルによる列車遅延を減らすため、2003年4月5日にLine 42/43のダイヤに修正が加えられた。Linie 42は基本的に2編成併結、Linie 43は基本的に1編成単独での運転とされ、Köln Hbfでの併解結を極力減らすよう対策が取られた。 2003年5月5日より、DBとLufthansa AG / Frankfurt Flughafen AGの3社共同でのAIRail Serviceが、Köln Hbf - Frankfurt/M Flughafen間で開始された。AIRail Serviceは2001年よりStuttgart Hbf - Frankfurt/M Flughafen間で開始されたサービスで、乗客はKöln Hbfでチェックインを行い手荷物を預け、指定されたICEを航空便として利用することができる。AIRail Serviceの対象となるICEは、Line 42/43の31本(Köln-Frankfurt/M 15本 / Frankfurt/M-Köln 16本)の列車で、約1時間間隔となった。これらの列車にはLH 6802-LH 6832のフライトナンバーが与えられた。 AIRail Serviceの乗客は、First Class/Business Classの乗客はICEの1等車へ、Economy Classの乗客は2等車へ乗車し、乗客の荷物は、南行き列車では21号車ラウンジに、北行き列車では28号車ラウンジに搭載されている。荷物の搭載作業のため、各列車には2名ずつ係員が添乗しており、荷物が搭載されるラウンジはDortmund-Mannheimで閉鎖されている。 2004年ダイヤ (2003年12月12日改正)でICE Linie 41はEssen Hbf - Frankfurt Flughafen - Frankfurt Süd - Nuernberg Hbf (1往復はDortmund Hbf - Muenchen Hbf)となった。Frankfurt/M Hbfは列車回数が多く、遅延の原因となりやすいため、Hbfを通らずFrankfurt Süd経由となった。 2005年ダイヤ (2004年12月10日改正)では、ICE Linie 40が廃止され、代わりにNBS Köln-Rhein/Mainの中間駅にLinie 79の列車が停車するようになった。この改正から、ICE Linie 79はベルギー国内のLeuven-Liegeが高速新線経由となり、Frakfurt/M-Brüesselは3時間32分に短縮された。ただし、高速新線ではThalysは最高300km/hであるのに対し、ICE 3は最高250km/hに制限された。 2005/2006冬ダイヤ (2005年12月11日改正)ではLinie 45は2往復を除いて、Köln-Mainzに短縮された。また、Köln-Stuttgart間にICE-Sprinter 1往復が新設された。なお、改正を前に、2005年11月から403形2次車の納入が開始され、11月27日München発Dortmund行ICE 512にTz 353+Tz 355が投入されたのを皮切りに、順次就役した。運用上は1次車と2次車は区別されなかった。 サッカーのドイツ・ワールドカップ開催を前に、2006年夏ダイヤ (2006年5月28日)ではNürnberg - München間の路線改良が完成し、SFS Nürnberg - Ingolstadt (89km)で最高300 km/h、改良新線ABS Ingolstadt-München (82km)で最高200k/hでの運転が可能となった。ICE Linie 41はこの新線を利用し、Essen Hbf - Frankfurt Flughafen - Frankfurt Süd - Nürnberg Hbf - München Hbfに延長され、Nürnberg -Münchenは所要時間が100分から約80分に短縮された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年ダイヤ (2006年12月10日改正)、ICE Linie 41がそれまでの2時間間隔から1時間間隔となり、Nürnberg-Ingolstadtは最速62分まで短縮された。Linie
41は全列車がKöln Messe/Deutz・Frankfurt Süd経由からKöln Hbf・Frankfurt
Hbf経由に変更された。前者はMese/Deutz駅の工事によるもの、後者はFrankfurt Süd乗換えが乗客に不評であったための措置であった。なお、Hbf経由となったことで遅延が予想されるため、Köln
Hbf - Frankfurt Flughafen間はノンストップとなった。また、北側の発着駅はこれまではEssenが基本であったが、半数程度の列車はKöln、Düsseldorf、Oberhausenなどに変更された。Linie
41の増発に必要な車両数を確保するため、ICE Linie 40 (Münster - Frankfurt) / Linie 47
(Köln - Stuttgart)の2路線が廃止され、Linie 43 (Dortmund - Basel)は大半の列車がKöln
Hbf - Basel SBB間の運転となった。また、Linie 45 (Köln - Mainz - Stuttgart)は5往復に減便され、Mainz
- Stuttgart間の運転は取り止められた。一方で、主に通勤客向けにICE-Linie 49 Köln Hbf - Frankfurt
Hbfが新設された。この路線はSieburg/Bonn・Montabaur・Limburg Sued全駅停車となった。 2007年夏ダイヤ (2007年6月10日改正)では、フランスの高速新線LGV東ヨーロッパ線 (Paris - Strasbourg)が開業し、ドイツ・フランス間のICE ・TGVの相互直通乗り入れが開始された。ICEはFrankfurt /M - Mannheim - Saarbrücken - Parisの運転で、Parisのターミナルは東駅Paris Gare de l'Estとなった。ICEは3往復が設定されたが、そのうち2往復はSaarbruecken - Parisのみの運行で、SaarbrueckenでFrankfurt/M方面とのICと接続した。LGV東ヨーロッパ線では当時世界最速の最高320km/h運転を行い、Frankfut/M - Parisは従来の所要時間6時間15分から約4時間に短縮された。直通運転開始時点ではフランス直通用のICE 3MF編成はTz 4680-4683の4編成が用意され、最初のFrankfurt/M Hbf発Paris Gare de l'Est行ICE 9558にはTz 4681が使用された。 2008年ダイヤ(2007年12月9日改正)では、ICE 3MFは6編成が出揃い、全列車がFrankfurt/M - Paris直通運転となり、5往復に増発され、所要時間も3時間50分に短縮された。この他では、ICE Linie 41は大半の列車がDortmund発着に戻され、ICE Linie 42のうち1往復は、Bremen経由でHamburgまで延長された。 2008年7月9日にはICE 518 がKöln Hbfを発車した直後に脱線した。7月11日から緊急点検が実施され、ICE 3全67編成のうち61編成が運用から外れた。ICE 3使用列車の運行区間の短縮や運休、ICE 3以外の車両による代走が行われたが、ダイヤは大幅に乱れた。特に7月11日はICE 3の残った6編成がKöln - Frankfurt(M)を往復するのみであったが、検査終了とともに順次運用に復帰し、7月15日には一部列車の編成短縮、運行区間短縮を残すのみで、ほぼ正常化した。 2008年10月にはICE-Tの車軸に定期検査で亀裂が発見されたのに伴い、超音波検査の間隔が短縮された。これに伴う編成数不足に対応するため、DBは2008年10月15日からICE 3の2編成併結列車を単編成化し、列車数は極力確保する措置を取った。2008年10月20日からはさらに大幅な変更を加えた。ICE Linie 41はDortmund - Frankfurt/M、Linie 42はKöln - Stuttgartにそれぞれ短縮され、残った区間は機関車牽引列車による代走とされた。Linie 43は単編成による運行とされた。Linie 45/49の運行は取り止められ、他の路線の列車の停車駅を増やしたり、代替の交通手段で対応された。2008年12月14日からは、2009年6月14日のダイヤ改正までの間に集中的に検査を行うため、ICE Linie 42の一部はStuttgart発着、Linie 43の一部はKarlsruhe発着に短縮され、残りの区間はICで補完された。 ICE 3MFの慢性的な車両不足の改善は短期的に難しいと考えられたため、2009年4月20日からはFrankfurt/M - ParisのICE 5往復のうち、ICE 9553/9552の1往復がTGV-POSによる運行となり、TGV 9553/9552となった。 2009年6月14日のダイヤ改正では検査体制の改善に伴い、運用編成数が増えた。ICE Linie 42はDortmund - Stuttgart - Muenchenの運行に戻された。ICE 45/49の運行も再開されており、ICE 3の運行はほぼ正常化した。また、ベルギーで高速新線HSL 3がLiege - Aachen間で開通し、ICE Linie 79は高速新線経由となり、Frankfurt/M - Brüsselは約30分短縮され、所要3時間6分となった。 DBは現在、403形50編成、406形13編成を所有しており、403形はBW München Süd、406形はBW Frankfurt/M Griesheimに集中配置されている。NSにも406形3編成が所属している。ICE 3の主な運行路線は以下の通りである。 -ICE Linie 41 Essen - Köln Messe/Deutz - Frankfurt/M - Nürnberg - München -ICE Linie 42 Dortmund Hbf - Köln - Frankfurt Flughafen - Stuttgart - München -ICE Linie 43 Köln - Frankfurt Flughafen - Karlsruhe - Basel -ICE Linie 45 Köln - Limburg Süd - Wiesbaden - Mainz -ICE Linie 49 Köln - Limburg Süd - Frankfurt/M -ICE Linie 78 Amsterdam - Köln - Frankfurt/M -ICE Linie 79 Bruessel - Aachen - Köln - Frankfurt/M -ICE Linie 82 Frankfurt/M - Saarbrücken - Paris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来の計画 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 3は2030年頃まで使用される予定であり、今後もドイツ鉄道の長距離輸送において中心的な役割を果たすことになる。2016年からは順次リニューアル工事も行われる予定である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸元表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Links |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ICE3-NS starts commercial operation (Aibaさん) ICE Internationalの営業運転開始の模様を掲載しています。 - Railroad Info Page (tdsatohさん) ICE 3の乗車レポートが豊富な写真と共に掲載されています。また動画も収録しており、発車音が楽しめます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考) ・Deutsche Bahn AG http://www.bahn.de ・ICE-Neue Zuege fuer Deutschlands Schnellverkehr, Daniel Riechers, transpress Verlag, 2001 ・ICE High-tech on rails, Wolfram O. Martinsen, Theo Rahn, Hestra-Verlag, 1996 ・ICE Geschichte・Technik・Typen, Wilfried Walter, GeraMond Verlag, 2001 ・Alles ueber den ICE, Dieter Eikhoff, transpress, 2006 ・InterCityExpress (Eisenbahn-Bildarchiv - Band 22, Georg Wagner, EK-Verlag, 2006 ・The Multiple-Unit Train for the European High-Speed Network - ICE 3 for German Railways and Netherlands Railways, Siemens ・DB-Triebfahrzeug-Lexion 2001, EK-Verlag, 2001 ・DB-Lokomotiven und Triebwagen Stand: 1. Juli 2001, EK-Verlag ・Eisenbahn Journal Special 5/99 Die ICE Familie, Hermann Merker Verlag, 1999 ・Eisenbahn Journal Special-Ausgabe 3/2002, Tempo 300-Die Neubaustrecke Köln-Frankfurt, Hermann Merker Verlag, 2002 ・Eisenbahn Journal Extra 1 - Die ICE-Story, Hermann Merker Verlag, 2005 ・BAHN EXTRA Bahn-Jahrbuch '99, GeraNova Zeitschriftenverlag, 1999 ・BAHN EXTRA Bahn-Jahrbuch 2001, GeraNova Zeitschriftenverlag, 2001 ・BAHN EXTRA Bahn-Jahrbuch 2002, GeraNova Zeitschriftenverlag, 2002 ・BAHN EXTRA Bahn-Jahrbuch 2003, GeraNova Zeitschriftenverlag, 2003 ・BAHN EXTRA Bahn-Jahrbuch 2004, GeraNova Zeitschriftenverlag, 2004 ・BAHN EXTRA Bahn-Jahrbuch 2005, GeraNova Zeitschriftenverlag, 2005 ・BAHN EXTRA Bahn-Jahrbuch 2006, GeraNova Zeitschriftenverlag, 2006 ・BAHN EXTRA Bahn-Jahrbuch 2007, GeraNova Zeitschriftenverlag, 2007 ・Eisenbahn Kurier 2/2003 ・Lok-Report 8/2006 ・Fahrzeug-Katalog 2001 Akutuall: Alle Tribfahrzeuge der DB, GeraNova Zeitschriftenverlag, 2001 ・Today's Railways No.61/69/71/74/79/82/83/84/85/86, Platform 5 Publishing, 2000-2003 ・The European Railway Server http://mercurio.iet.unipi.it/ ・Eisenbahn Kurier http://www.ek-verlag.de/ ・GeraNova http://www.geranova.de/ ・Lok-Report http://www.lok-report.de/ ・ICE-Fanpage http://www.ice-fanpage.de/ ・The ICE/ICT Pages http://mercurio.iet.unipi.it/ice/ice.html ・ICE-Networld http://www.ice-networld.de/ ・ICE-Fansite http://www.ice-fansite.de/ ・ICE-Page http://www.ice-page.de/ ・Peter Schokkenbroek's Homepage http://home.hetnet.nl/~pschokk/ ・Homepage ueber die schnellsten Zuege der Welt http://www.hochgeschwindigkeitszuege.com/ ・鉄道ファン 10/1995, 11/1996, 11/1999, 11/2002, 交友社 ・鉄道ジャーナル 12/1999, 11/2002, 12/2002, 鉄道ジャーナル社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update: 08.08.2014 Photo by Takao Satoh, Nanna Go, Nils Hennemann, Akihiro Satoh, Koji Abe, PPL.inc, Hisayuki Katsuyama Text by Hisayuki Katsuyama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||